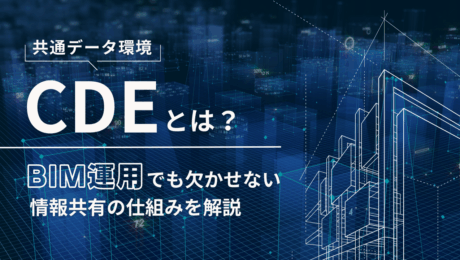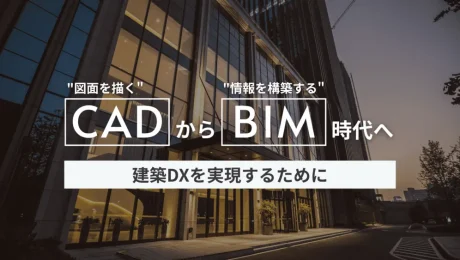WORKS&TOPICS
WORKS&TOPICS
2025.11.17
COLUMN BIM
BIM教育とは何か?操作研修では定着しない理由と「概念理解」から始める導入ステップ

近年、建築業界では、図面中心の業務からデジタルデータを軸とした業務へ移行する「建築DX」が求められています。その中心に位置づけられるのがBIMです。しかし、BIMを導入したものの、「現場で活用されない」「業務効率が上がらない」といった課題は多くの企業で見られます。その原因の多くは、BIMを“ソフトの操作スキル”として教育してしまうことにあります。
本来、BIMは3Dモデルを作るためのツールではなく、建築情報を整理・共有し、プロジェクト全体で活用するための情報マネジメント手法です。
そのため、BIM教育の出発点は操作ではなく、「なぜ情報を一元化するのか」「どのように共有・更新すべきか」という概念の理解にあります。
本記事では、なぜ操作研修だけではBIMが定着しないのかという背景から始め、BIM教育の核心となる「情報をどのように管理・共有すべきか」という視点を整理します。さらに、ISO19650に基づいた概念理解をどのように実務へ落とし込むのか、そしてその学びを組織全体に根づかせるための仕組みづくりについて、段階的に解説していきます。
なぜBIM導入は定着しないのか
BIMを導入したにもかかわらず、実務にうまく活用されなかったり、担当者だけに負荷が集中したりするケースは少なくありません。
この問題はツールの難易度や個人のスキルだけが原因ではなく、BIMをどのように扱うべきかという前提の理解が組織内で揃っていないことにあります。
操作研修に偏ることで生まれる限界
導入段階では、ソフトの操作方法を学ぶ研修から始まることが一般的です。
モデリングや図面生成など、手を動かす技術は学びやすく、習得状況も目に見えやすいためです。
しかし、操作ができるようになったとしても、情報をどの段階で入力し、誰が更新し、その情報が次工程でどのように使われるのかといった判断基準が共有されていなければ、BIMは組織的な仕組みとして機能しません。
こうした前提が揃っていないまま運用を始めると、担当者ごとにモデルの作り方や情報の精度にばらつきが生まれ、BIMは個々の技量に依存した状態になってしまいます。
BIMが個人のスキルで止まってしまう理由
BIMはもともと、関係者が同じ情報に基づいて業務を進める「チームでの情報共有」を前提とした仕組みです。
しかし、情報の扱い方に関する共通理解がなければ、現場では次のような状態が起こりやすくなります。
- ・モデルの構築方法が担当者ごとに異なる
- ・入力される情報の粒度が統一されない
- ・情報更新や引き継ぎが個人に依存する
- ・手戻りや再作業が繰り返される
ここで起きている問題の本質は「操作が習得できていないこと」ではありません。 情報をどのように整理し、共有し、活用するのかという基準が揃っていないことが原因です。
BIM教育の役割は共通言語を揃えること

BIMを活用する目的は、3Dモデルを作成することそのものではありません。設計から施工、維持管理まで、一つの情報を軸に業務をつないでいくことにあります。
そのため、まず必要なのは「どの情報を、どのような考え方で扱うのか」という認識を、メンバー間で揃えることです。
この「前提の共有」が揃っていなければ、どれだけ操作スキルを学んでも、運用は安定しません。反対に、情報を扱う基準が揃っている組織は、担当者が変わってもプロジェクトが乱れにくく、属人化を抑えることができます。
BIMはツールではなく情報を扱う仕組み
BIMは、設計者がモデルを作るためのソフトではなく、プロジェクト全体で情報を扱うための仕組みです。情報をどの段階で生成し、どのように更新し、誰が責任を持って管理するのかといった整理ができていると、チーム全体が同じ基準で進行できます。
モデルはそのための媒体にすぎません。重要なのは、情報を扱う考え方が揃っていることです。
ISO19650が示す「情報を扱う基準」
情報の扱い方には、国際的な標準としてISO19650があります。この標準では、情報を次の流れで整理することが推奨されています。
- ・生成する
- ・共有する
- ・確認する
- ・保存する
これは特別なやり方ではなく、「誰が・どの情報を・いつ・どの精度で扱うか」を揃えるための基礎となる考え方です。BIM教育でまず学ぶべきは、この枠組みそのものと言えます。
概念理解がなければ運用は成立しない
操作スキルだけを先に身につけても、運用が安定しないのは、判断の基準が人によって違うためです。 考え方が共有されていれば、プロジェクトごとの進め方やモデリングのルールに一貫性が生まれます。
教育の役割は、 「どう作るか」より先に「なぜそのように扱うのか」を揃えること。
ここが揃うと、その後の操作習得や実務適用がスムーズになります。
概念理解だけでは組織は変わらない
情報の扱い方に関する共通理解は、BIMを導入するうえで欠かせない土台です。
しかし、概念を理解しただけでは、実務が変わるわけではありません。BIMは日々の業務のなかで使われてはじめて定着します。
概念理解は「スタートライン」であり、組織改革そのものではないという点が重要です。
概念は判断基準を揃えるための土台
概念理解によって、情報の入力や更新の判断基準がチーム内で揃います。これにより、作業方法が個々の経験に依存する状態を避けられます。
ただし、基準が揃っただけでは、現場でその基準が自然に運用されるとは限りません。
基準と実務のあいだには「どう使うか」を体験して習得する時間が必要です。
実務で使って、はじめて定着する
実際のプロジェクトでモデルを共有し、情報を受け渡しながら進める体験があると、概念は業務の中に根づきます。ここで重要なのは、操作を教えることではなく、業務の流れのなかで「情報がどのように使われているか」を理解することです。
運用を支える仕組みが組織定着をつくる
BIMを組織で継続するためには、個人ではなくチームで回せる仕組みが必要です。
たとえば、命名ルール、図面・モデルの更新手順、情報の引き継ぎ方法など、プロジェクトを支える基本的なルールが整備されていることが重要です。
仕組みが整っている組織は、担当者が変わってもBIMが継続します。
逆に、仕組みがない組織は、担当者に依存し、BIMが続きません。
段階的に進めるBIM導入の3ステップ

BIMを定着させるには、「教育 → 実務 → 仕組み化」という順序で段階的に取り組むことが重要です。
一度にすべてを変えようとするのではなく、基礎となる考え方から運用ルールまでを、無理なく積み上げていきます。
ステップ1|概念理解と共通認識の形成
最初に行うべきは、BIMをどのように位置づけ、どのように情報を扱うのかという前提を揃えることです。ここでは、ISO19650に基づいた情報管理の流れを理解し、チームで共通した判断基準をつくります。
この段階が揃うことで、操作を学ぶ際の迷いや個人差が減り、組織としての「使い方」が定まります。
ステップ2|実プロジェクトでの運用と習熟
概念を理解したら、それを実際の業務のなかで使ってみます。
小規模なプロジェクトや一部工程から始めることで、無理なく業務に馴染ませることができます。ここで重要なのは、操作を覚えることではなく、情報の受け渡しや更新の流れを体験することです。 “使える状態”は、実務の中で確立されます。
ステップ3|CDEとルール整備による定着・標準化
運用が回り始めたら、情報を蓄積し、再現性を持って扱える仕組みに整理します。CDE(共通データ環境)の活用や、命名ルール、モデル更新手順などの基準を整えることで、担当者が変わっても同じ品質で運用が続けられます。
ここで初めて、BIMが「人ではなく組織で扱うもの」として定着します。
ixreaの提供モデル|教育から運用へつながる支援

BIMを組織に根づかせるには、概念を理解する段階と、実際の業務の中で使いながら運用を整えていく段階が必要です。
ixreaでは、この流れを分断せず、段階的につながる形で支援しています。
オンラインで学べる概念教育(BIMマスターラーニング)
まず、ソフト操作に入る前に、BIMを「情報を扱う仕組み」として理解します。
ISO19650に基づき、情報をどのように整理し、共有し、更新していくのかという考え方を学ぶことで、組織内での判断基準が揃います。
この教育はソフトに依存しないため、役割や経験が異なるメンバー間でも、共通認識をつくりやすいことが特徴です。学べる内容は次のとおりです。
- BIMを「情報基盤」として扱うための基本概念
- ISO19650が示す情報マネジメントの流れ(生成 → 共有 → 確認 → 保存)
- CDEにおける情報の受け渡しと責任範囲の考え方
- 情報をいつ・誰が・どの精度で入力するかという判断軸
ここで形成される「共通言語」が、後の運用フェーズを支える土台となります。
実務に寄り添うコンサルティング(操作・運用支援)
概念を理解しても、現場で使わなければ定着は進みません。
そこで、実際のプロジェクトに並走しながら、モデルの構築方法や情報の受け渡し手順を一緒に整理していきます。必要に応じてソフト操作についてもサポートし、現場で迷わず進められる状態をつくります。
学習と実務が行き来することで、BIMは「知っていること」から「使えること」へ変わり、組織として扱える仕組みへと育っていきます。
BIM教育は組織づくりの土台になる
建築DXを進めるうえで、BIMは単なるツールではなく、組織で共有される情報基盤となる存在です。そのため、BIMを組織に定着させるためには、まず「情報をどのように扱うか」という考え方を揃えることが必要です。
操作スキルだけでは、担当者ごとに進め方が分かれ、運用が属人的なままになってしまいます。
情報の整理・共有・更新の基準が共有されていれば、実務での判断が揃い、BIMは個人の技術ではなく、組織として扱える仕組みへと育っていきます。
BIM教育は、そのための 最初の一歩 となります。
まずは、組織として「BIMをどう捉えるのか」という認識を揃えるところから始めてみてください。
ixreaでは、その基盤となる考え方を ISO19650に基づいて体系的に学べるオンライン学習コンテンツとして提供しています。
概念が共有されることで、実務での判断が揃い、BIMは組織として扱える仕組みへと育っていきます。そのうえで、運用やルール整備へと段階的に進めていくことが大切です。
BIM運用の土台づくりから、着実に進めていきましょう。