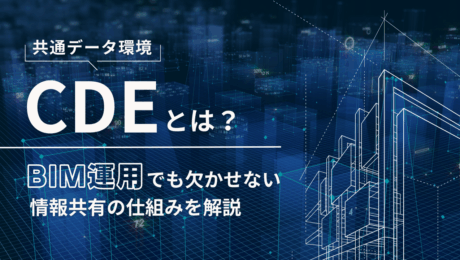WORKS&TOPICS
WORKS&TOPICS
2025.10.28
COLUMN BIM
BIMとCADの違いから見る、建築設計の新しい考え方
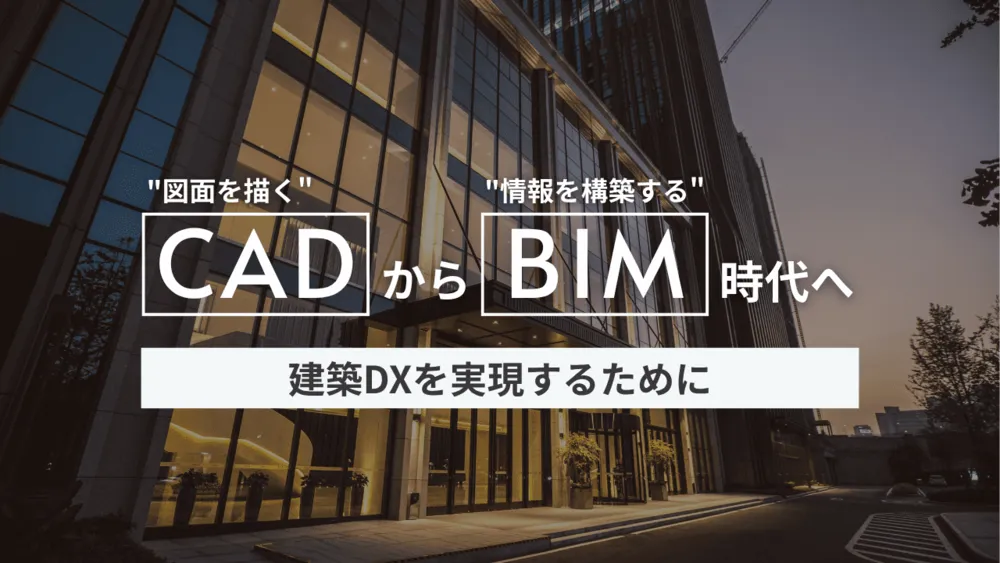
建築設計の現場はいま、大きな転換期を迎えています。建設DXを実現するためには、単に図面を描くだけではなく、設計情報を「活用できるデータ」として構築することが求められています。その中核を担う概念がBIMです。これまでのCADのように“線を描く”だけの時代は終わり、BIMによって建物に関わるあらゆる情報を一元的に扱うことが可能になりました。
BIMは、設計・施工・維持管理を通してデータを連携させる技術であり、建設DXを進める上で不可欠な基盤です。設計者は、形を描くことよりも、建物に関する“情報”をどう生成し、どう共有し、どう活用するかが問われる時代に入っています。
図面を描くCAD、情報を構築するBIM。
この違いが、設計の「標準」を塗り替えています。
CADとBIMは何が違うのか?
CAD:図面を描くためのツール
CAD(Computer Aided Design)は、設計の精度と効率を高めるために誕生しました。
紙の図面をデジタル化し、正確な寸法で線を引くことができる。それが建築設計の標準ツールとして長く使われてきました。
ただし、CADはあくまで作図ツールです。図面同士は独立しており、変更があるたびに立面・断面・構造図・設備図を手作業で修正しなければなりません。
プロジェクトが複雑になるほど、整合性チェックに多くの時間を取られてしまいます。
BIM:建築情報を統合的に扱う仕組み
BIM(Building Information Modeling)は、建築物を三次元モデルで構築し、そこに様々な属性情報(材料・コスト・法的構造的要件など)を付与することで、必要な情報をまとめていく仕組みです。
ひとつのソースを確認すれば、建築に関わる正しい情報を素早く確認することができます。
つまりBIMは、「描く」ためのものではなく必要な情報を「管理する」ための仕組み。
建物のライフサイクル全体で、データを一貫して活かせます。
| 比較項目 | CAD | BIM |
| データ構造 | 2D(線) | 3D+属性情報 |
| 情報の関係 | 独立(手動修正) | 連動(自動更新) |
| 主な目的 | 図面作成 | 情報共有・意思決定支援 |
| 活用範囲 | 設計中心 | 設計〜施工〜維持管理まで |
図面を描くから、情報を構築する時代へ

BIMでは、一つのオブジェクト(柱や壁など)に複数の情報を持たせられます。
素材、コスト、施工時期、メンテナンス周期など、あらゆる情報をデジタルデータとして管理することができます。設計段階から施工、維持管理までの連携をスムーズにし、業務全体の精度を高めます。
例えば、設計に必要な情報が一つに纏まることで、下記のようなメリットが考えられます。
- ・不整合のない一貫した正しい図面を簡単に出力できる
- ・関係者が同じデータを見て確認することで、齟齬を減らせる
- ・数量拾い出しの自動化
- ・材料コストの即時算出
- ・干渉チェック
これまでアナログで人の目と手によって行ってきた作業を、早い段階からデータを活用して自動化することができます。
BIMは「図面を減らす」技術ではなく「一貫性、正確性を担保する」技術。この違いこそが、設計業務を作図から情報マネジメントへと変える鍵です。
BIMがもたらす「情報の一貫性」と連携の力

BIM最大の価値は情報の一貫性です。
設計・施工・維持管理がひとつのデータでつながることで、プロジェクト全体の意思決定が速く、正確になります。設計・施工・運用の境界が薄れ、よりシームレスな体制が実現します。
特に次のような効果が得られます。
- ・設計変更が即座に他モデルへ反映される
- ・変更内容や変更履歴もデータとして蓄積される
- ・干渉チェックによりエラーの早期発見が可能
- ・数量やコストを自動集計できる
- ・竣工後の維持管理データとして再利用できる
近年では、クラウド環境やCDE(Common Data Environment)の活用も進み、遠隔地でも同じモデルをリアルタイムに編集・共有できるようになりました。設計事務所・施工会社・発注者が、物理的距離を超えて同じ情報を見ながら判断を下せます。
「感覚的な判断」から「データに基づく判断」に変化していくことで、プロジェクト全体の品質と透明性を底上げできます。
BIMはもはや作図ツールではなく、情報マネジメントの基盤です。
関係者が同じモデルを見て議論できることで、認識のズレが劇的に減ります。
現場が感じるBIM導入の壁
BIMには多くの利点がある一方で、導入時のハードルもあります。
ツールの習熟コストやソフト導入費用、協力会社との連携。
特に小規模な設計事務所では、「コストが見合うのか」「教育に時間が割けるか」といった不安の声も少なくありません。
しかし、すべてを一度に変える必要はありません。
基本設計だけBIM化する、数量拾い出しだけBIMで行うなど、部分導入から始めることで確実に成果を出す事例も増えています。
BIM導入とは、「一気に変えること」ではなく、「できる範囲から変えていくこと」。
その積み重ねが、組織全体の情報設計力を高めます。
BIMがもたらす設計ワークフローの変化

BIM導入によって、設計プロセスやチーム内の役割分担が大きく変わります。
設計者が図面整合作業に追われる時間を減らし、分析・提案といった価値創出型の業務に集中できるようになります。
導入後によく見られる変化としては次のようなものがあります。
- ・図面整合チェックが自動化され、検証が迅速化
- ・3Dモデルを用いた打ち合わせでクライアント理解が向上
- ・現場担当者とのコミュニケーションがスムーズに
- ・施工段階での手戻りが減少
BIM導入の本質は、正確なモデルを作ることではなく、正確な判断を早く下せる環境を整えることにあります。
BIMが広がる背景と業界の流れ
国交省は2023年以降、公共建築でのBIM活用を原則化しました。地方自治体でも、BIMを条件にしたプロポーザル案件が増加しています。
また、民間案件でもBIMデータ活用が求められるケースも増えてきています。設計から施工、維持管理に至るまで、BIMは建築業務全体をつなぐ新しい標準へと進化しています。
BIM普及を後押しする要因は以下の通りです。
- ・国や自治体の推進方針
- ・中小設計事務所向け支援制度
- ・BIM教育・人材育成の拡充
BIMは、もはや一部企業の専有技術ではなく、設計・施工・維持管理のすべてを支える業界共通の基盤となっています。
設計の「標準」は、情報を扱うこと。
BIMは、建築を「線で描く」時代から「情報を扱う」時代へと変える仕組みです。CADが作図の効率化を支えてきたように、BIMは情報の共有と精度向上を支える役割を担っています。
BIMを導入することで、設計事務所は「作業型の設計」から「思考型の設計」へと進化します。図面チェックや整合作業に費やしていた時間を、クライアントへの提案や空間品質の向上へと振り向けることで、プロジェクト全体の透明性と生産性が高まります。
また、BIMの普及によって、設計の評価基準も変化しています。
図面の美しさだけではなく、情報の正確性、共有性、意思決定の速さが新たな価値基準となっています。いま求められているのは、BIMを使うことではなく、情報をマネジメントする力を備えた設計者です。
BIM導入はツール変更ではなく、組織の情報マネジメント力を高めるための第一歩です。
BIMの導入や運用について 「自社ではどこから始めるべきか」「最適な進め方を知りたい」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。
ixreaでは、設計事務所や施工会社を中心に、 初期導入設計・教育・運用体制構築・実案件支援を一貫して行っています。 現場の規模や目的に合わせ、最も効果的なBIM活用プランをご提案します。