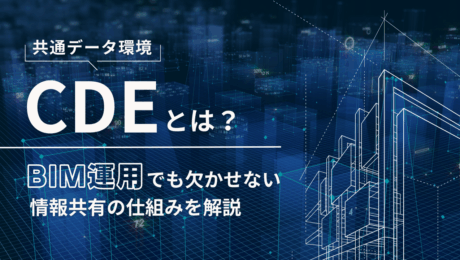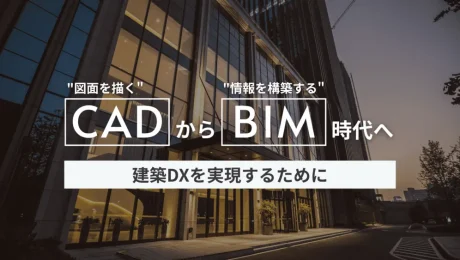WORKS&TOPICS
WORKS&TOPICS
2025.10.28
COLUMN BIM
ISO 19650とは?BIM導入を成功に導く国際規格と実務への活かし方

建築業界では今、BIM導入が進んでいます。その中で注目されているのが、BIM運用を国際的に標準化する規格「ISO 19650」です。
ISO 19650は、BIMを活用するプロジェクトにおける情報の管理・共有・活用方法を国際的に統一したルールであり、BIMの考え方を理解するうえで押さえておきたい指針のひとつです。
BIMを単なる3D設計ツールではなく「情報マネジメントの基盤」として活用するために重要な枠組みといえます。
本記事では、ISO 19650の概要と構成、実務への活かし方を整理し、BIMの導入・活用を進める上で業務にどう取り入れるべきかを解説します。
ISO 19650とは?
ISO 19650は、建設プロジェクトにおける情報マネジメントの国際標準を定めた規格です。
設計・施工・維持管理に関わる膨大な情報を、建物のライフサイクル全体で一貫して管理・共有することを目的としています。
従来のプロジェクトでは、設計図・仕様書・施工図・検査記録などの情報が部署や企業ごとに分断され、重複や伝達ミスが発生しやすいという課題がありました。ISO 19650は、こうした問題を解決するために、「情報を資産として扱う(Information as an Asset)」という考え方を提唱しています。
もともとは英国で策定された「PAS 1192」シリーズをベースに、国際標準化機構(ISO)が世界共通の枠組みとして整備したのがISO 19650シリーズです。これにより、国や企業の垣根を越えて、統一された基準でBIMを運用・連携できるようになりました。
BIMが建築情報を統合的に構築・可視化する仕組みだとすれば、ISO 19650は、その情報をどのように整理・共有・活用するかを定義する国際的なルールです。両者をセットで理解することで、BIMをより実務的に活かし、プロジェクト全体で情報をつなぐ仕組みへと発展させることができます。
ISO 19650の構成と各パートの役割

ISO 19650シリーズは、BIMを活用する際に必要となる情報マネジメントの枠組みを、建築プロジェクトの各段階(設計・施工・維持管理など)に沿って整理した体系的な規格です。
それぞれのパートが「どの段階で、誰が、どの情報を、どのように扱うか」を定義しており、 BIMを実務で運用するうえでの情報管理の設計図といえます。
ここでは、主な5つのパートを中心に、その役割と実務上のポイントを整理します。
Part 1(ISO 19650-1):基本概念と原則
シリーズ全体の基礎を定義するパートで、BIMを設計ツールではなく、プロジェクト全体で情報を共有・活用するための仕組みとして位置づけています。
ここで重視されているのは、「図面やモデルは完成したら終わり」ではなく、建物のライフサイクル全体で活かすべき「情報資産」であるという考え方です。
BIMでは、図面を納めて完結させるのではなく、その先の工程でも活かせる“情報”として引き渡すことが重視されます。この考え方をチーム全体で共有することが、BIMを実務に根づかせる第一歩となります。
Part 2(ISO 19650-2):設計・施工段階の情報マネジメント
実務で最も利用されるパートで、設計から施工までの情報の流れを整理しています。
発注者と受注者の間で「どの情報を・いつ・どの形式で・どの精度で扱うのか」を明確にし、 曖昧になりがちな情報管理を標準化します。
代表的な要素は次の通りです。
- ・EIR(Employer’s Information Requirements):発注者が求める情報要件
- ・BEP(BIM Execution Plan):受注者が情報をどう作成・管理するかの計画
- ・TIDP/MIDP:個別タスク・全体スケジュールの情報計画
これらを明確に定義することで、干渉チェックのタイミングやIFC形式での納品可否など、
実務上の判断を事前に統一できます。
Part 3(ISO 19650-3):維持管理段階の情報マネジメント
建物が完成した後、運用・保守・更新といった維持管理フェーズで情報をどう活かすかを示すパートです。
たとえば、設備点検履歴、交換部材の型番、保守周期といった情報をBIMモデルに紐づけることで、維持管理者は必要なデータを即座に把握できます。これにより、紙資料の参照や引き継ぎ時の情報欠落を防ぎ、FM(ファシリティマネジメント)の効率化が可能になります。
国内でも、空港や大学病院など大規模施設で、BIMをFMシステムと連携させる運用が始まっています。
Part 4(ISO 19650-4):情報交換の仕様
Part 2・3で定義された情報を、実際にどのような形式・手順で共有・納品するかを定めたパートです。情報の品質・形式を標準化することで、異なる組織間でも整合性の取れた情報連携を実現します。
主な内容は以下の通りです。
- ・情報要求の明確化:EIRに基づき、必要な精度や更新頻度を明示
- ・交換形式の統一:IFCやCOBieなど、国際的に認められた形式を採用
- ・納品手順の標準化:テンプレート化により、納品データの再利用性を向上
こうした仕様統一により、設計・施工・維持管理のすべての関係者が同じ情報をもとに判断できる環境を整えます。
Part 5(ISO 19650-5):情報セキュリティ管理
BIMデータには建物の構造・設備・セキュリティ関連情報など、機密性の高い情報が含まれます。 Part 5では、こうした情報を安全に扱うためのガイドラインを示しています。
主な要素は次の通りです。
- アクセス制御:ユーザー権限を細分化し、閲覧・編集を制限
- 通信の暗号化:データ転送時のセキュリティを確保
- リスクアセスメント:情報の重要度に応じて管理レベルを設定
セキュリティを担保することで、BIMデータを安心して共有できる体制を整えることが可能です。
ISO 19650の各パートを理解することは、BIMを「正確な情報を扱う仕組み」として実務に根づかせるために欠かせません。 BIMを本質的に活用するための第一歩として、情報をどのように整理し、共有していくかを学ぶことが重要です。
ISO 19650とCDE(共通データ環境)

ISO 19650を理解するうえで、あわせて知っておきたいのがCDE(Common Data Environment:共通データ環境)という考え方です。
CDEとは、建築プロジェクトに関わるすべての情報を一元的に管理し、関係者全員が常に最新のデータを共有できるようにするための仕組みを指します。
ISO 19650では、情報を「作成 → 確認 → 承認 → 共有 → 保存」という流れで扱うことが定義されています。このプロセスを実現する実務上の基盤となるのが、CDEの役割です。
たとえば、図面・モデル・仕様書・写真・検査記録など、従来は部署や企業ごとに分散していたデータを、 一つの環境で統合管理することで、情報の重複や整合性の問題を防ぐことができます。
CDEを活用することで、以下のようなメリットが得られます。
- ・情報の一元管理:データの混乱を防ぎ、必要な情報にすぐアクセスできる
- ・アクセス権限の制御:関係者ごとに閲覧・編集範囲を設定し、セキュリティと透明性を両立
- ・変更履歴の記録:誰がいつ修正したかを追跡でき、情報の正確性と信頼性を担保
これにより、古いファイルを誤って使用したり、担当者間でデータが食い違うといった
人的ミスを防止することができます。特に、設計・施工・維持管理といった異なるフェーズの情報をスムーズに引き継ぐうえで、 CDEはISO 19650の考え方を支える重要な要素といえます。
日本ではCDEの運用はまだ多くありませんが、BIMを単なる「設計支援ツール」ではなく、プロジェクト全体の情報基盤として活用するために、その仕組みを理解しておくことが今後ますます重要になります。
ISO 19650に関するよくある質問(FAQ)
Q1. ISO 19650は義務化されていますか?
日本国内では法的義務はありません。必ずしも準拠が前提となるわけではありませんが、BIMを理解する上で重要な指針のひとつです。国際的な動向を踏まえて、早い段階から基本概念を押さえておくと今後の対応がスムーズになります。
Q2. ISO 19650を導入するには何から始めればよいですか?
まずは社内の情報管理ルールを整理することから始めましょう。ファイル命名規則や保存形式、フォルダ構成を標準化するだけでも、ISO 19650の考え方に近づけます。
Q3. 中小企業でも対応は必要ですか?
現時点で義務ではありません。ただし、将来的に大手ゼネコンや自治体と連携する場面で参考になる可能性があるため、基礎知識として理解しておくと安心です。
Q4. CDE(共通データ環境)は必ず導入しなければなりませんか?
必須ではありません。ただし、情報共有やバージョン管理を効率化するうえで、CDEの仕組みは非常に有効です。BIMを実務に落とし込む際の基盤として、段階的に導入を検討する価値があります。
Q5. ISO 19650とPAS 1192の違いは?
ISO 19650は、英国規格であるPAS 1192を国際規格化したものです。基本的な考え方は共通していますが、国際適用を前提に表現や運用範囲が整理・拡張されています。
Q6. RevitやArchicadなどのBIMソフトとの関係は?
ISO 19650は特定のソフトウェアに依存しない「情報マネジメント規格」です。どのBIMソフトを使っても、情報の構造や命名ルールをISO 19650に沿って整理することで、データの再利用性と共有性を高められます。
Q7. ISO 19650が日本であまり使われてないのであれば、学ぶ必要はありますか?
規格そのものに沿ってプロジェクトを進めるケースは少ないと思いますが、BIMを理解する上ではとても重要な知識になります。まずは基本概念を理解することが、BIMを推進するための第一歩です。
ISO 19650を理解することが、BIMを正しく活かす第一歩

ISO 19650は、BIMを活用するうえで国際的に通用する「情報マネジメントの基盤」となる規格です。日本では現時点で義務化されていませんが、BIMを単なる3D設計ツールではなく、建築情報を資産として扱う仕組みへと発展させるために欠かせない考え方を示しています。
重要なのは規格そのものを覚えることではなく、その考え方をどう実務に取り入れるかです。 社内の情報管理ルールや命名規則を見直し、データ共有の仕組みを整えるだけでも、ISO 19650の理念に一歩近づくことができます。現場に合わせた教育や外部支援を取り入れながら、段階的に定着させていくことが、BIM活用を成功に導く鍵です。
ixreaでは、ISO 19650の規格理解から実務導入・教育支援までを一貫してサポートしています。CDE(共通データ環境)の導入支援や情報マネジメント体制の設計、現場向けBIM教育など、企業の課題に応じた実践的な支援を行っています。
効果的なBIM運用を実現するためには、理解と実践の両立が不可欠です。まずは、自社に最適な導入ステップを一緒に検討してみませんか。
\ISO 19650準拠 BIMの基礎から応用まで学べる オンライン学習コンテンツ/
BIMマスターラーニングの詳細はこちら