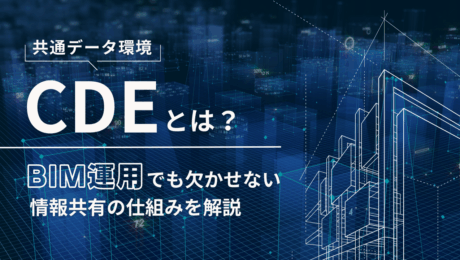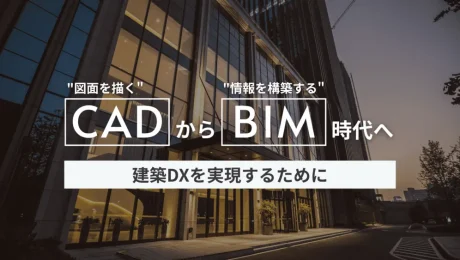WORKS&TOPICS
WORKS&TOPICS
2025.09.16
COLUMN
宿泊施設設計で必ず押さえるべき法制度・費用・設計ポイント
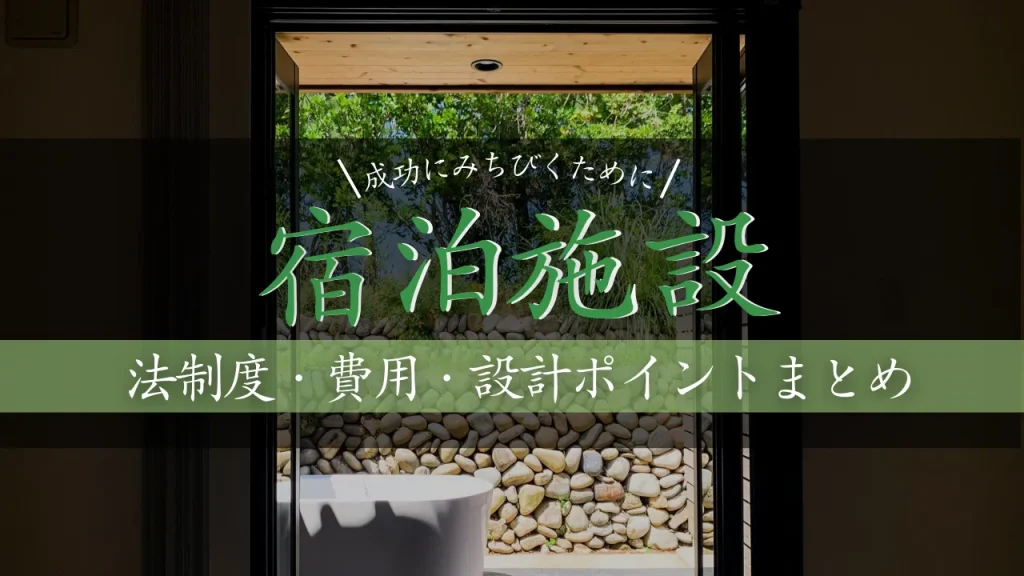
近年、観光需要の高まりやインバウンド回復に伴い、ホテルや旅館をはじめとした宿泊施設の新設やリノベーションが各地で進んでいます。特に地方都市や観光地では、古民家や空きビルを宿泊施設へ転用するケースも増えています。
しかし、宿泊施設の設計は単なるデザインやレイアウトにとどまらず、建築基準法や旅館業法、消防法など複数の法制度に適合させることが不可欠です。これを正しく理解していないと、設計や工事が進んでも営業許可が下りない、追加工事でコストが膨らむといったリスクにつながります。
ixreaでは、こうした法規制を踏まえた設計支援を強みとし、用途変更や消防協議を含めたトータルプランニングを提供しています。本記事では、宿泊施設設計において必ず押さえておくべき法制度や注意点を整理し、失敗しないための実践的な設計ポイントを解説します。
宿泊施設設計の流れと基本ステップ
宿泊施設の設計は、建物を形にするだけではなく、運営効率や収益性を見据えて計画を立てる一連のプロセスです。大まかな流れは以下のとおりです。
1. 市場調査と立地選定
ターゲット層や観光需要を把握し、設計コンセプトに合った立地条件を選定します。都市型ビジネスかリゾート型かによって、必要な施設や動線計画が大きく変わります。
2. 営業形態に応じた設計要件の整理
ホテル、旅館、簡易宿所、民泊など、営業形態によって客室規模・共用部・法的要件が異なります。どの形態を採用するかを踏まえ、設計上の条件を早い段階で整理します。
3. 事業計画と設計プランの統合
客室数や共用部の規模、収益性、投資回収期間などを考慮し、設計プランに反映します。現実的な収益モデルと空間計画を両立させることが、宿泊施設設計の重要なポイントです。
宿泊施設の法制度(建築基準法・旅館業法・用途変更)

建築基準法では、宿泊施設は主に「ホテル・旅館」「下宿」「寄宿舎」「共同住宅」に区分されます。用途地域によっては建築が認められない場合もあるため、立地選定時から用途地域の確認が必須です。
建築基準法上の宿泊施設の区分
建築基準法では、宿泊施設は用途区分によって取り扱いが異なります。
| 用途区分名 | 内容 | 用途地域での制限 |
| ホテル・旅館 (第1種特定用途) |
短期滞在者を対象とする宿泊施設 | 第一種低層住居専用地域では原則不可 |
| 下宿 | 居住に近い長期滞在向け宿泊施設 | 住居系地域でも可 |
| 寄宿舎 | 学生・労働者等の共同居住施設 | 多くの地域で可 |
| 共同住宅 | 賃貸マンションなど。民泊転用ケースあり | 制限は比較的少ない |
➡ 設計事務所の実務感覚としては、「住宅用途から宿泊用途に変更できるか」が最大の分岐点となります。
※ 民泊に転用されるケースでは、元が「共同住宅」であっても「旅館業法上の施設」としての届出が必要になります。
旅館業法上の宿泊施設の区分
旅館業法では営業形態ごとに設備や営業日数の要件が変わります。
| 区分 | 主な特徴 | 備考 |
| 旅館・ホテル営業 | 客室多数・フロント設置、1泊単位の営業 | 和風・洋風問わず |
| 簡易宿所営業 | 雑魚寝やゲストハウスなど簡易形態 | ドミトリーや民宿に多い |
| 下宿営業 | 1か月以上の長期滞在向け | 民泊とは異なる |
| 特区民泊 | 国家戦略特区内で180日以内営業可 | 届出制、条件緩和あり |
| 住宅宿泊事業(民泊新法) | 年180日以内の営業 | 住宅宿泊事業法に基づく届出制 |
➡ 設計段階では「どの営業形態で許可を取るか」が、プランニングに大きく影響します。
建築基準法と旅館業法の整合性ポイント
両制度を個別に満たすだけでは不十分で、相互の整合性を取る必要があります。
| 項目 | 留意点 |
| 用途地域 | 建築基準法で宿泊施設用途が許可されている地域か確認 |
| 用途変更 | 200㎡超で「住宅→旅館」などに変える場合は申請が必要 |
| 消防法 | 防火区画・避難経路・警報設備の整備が必須 |
| 建築確認 | 増改築・用途変更時にも確認申請が必要 |
➡ 設計を進める際には、建築確認と消防同意を同時並行で行うのがスムーズです。
宿泊施設の具体的な分類例
建築基準法と旅館業法の区分を突き合わせると、施設タイプごとに次のように整理できます。
| 施設タイプ | 建築基準法上 | 旅館業法上 | 備考 |
| シティホテル | ホテル・旅館 | 旅館・ホテル営業 | RC造、各室個室 |
| 民宿 | 簡易宿所 | 簡易宿所営業 | 和室・家族経営が多い |
| ゲストハウス | 簡易宿所 or 下宿 | 簡易宿所営業 | ドミトリー型が主流 |
| 民泊 | 共同住宅等 | 住宅宿泊事業 | 民泊新法または特区民泊 |
➡ このように、建築基準法上の用途と旅館業法上の営業形態をセットで確認することが、宿泊施設設計の第一歩です。
設計段階で必ず考慮すべきポイント

宿泊施設の設計では、快適性やデザイン性だけでなく、法規制・安全性・運営効率を同時に満たすことが不可欠です。ここでは、設計段階で特に重要となる実務的なポイントを整理します。
防火・避難計画(消防法対応)
宿泊施設は多くの人が利用するため、火災時の安全確保が最優先です。
消防法に基づく防火区画や避難経路の設計は、初期段階での検討が不可欠です。
- ・客室が2階以上にある場合は避難経路の確保が必須
- ・内装制限(不燃材の使用)や防火区画の設計を前提にプランニング
- ・消防との事前協議を設計段階で進めることで、工事後の手戻りを防止
衛生・設備要件(旅館業法・各自治体条例)
衛生面の基準は旅館業法や自治体ごとの条例で細かく定められています。
これを満たさないと営業許可が下りないため、設計時点での確認が重要です。
- ・客室面積や換気性能の基準を満たしているか
- ・トイレ・洗面・浴室の数が条例で定められた最低基準を満たすか
- ・フロントや共用スペースの設置が義務付けられている地域もある
バリアフリー対応とユニバーサルデザイン
高齢者や障害者を含む幅広い利用者に対応するため、バリアフリー設計は必須です。
近年はユニバーサルデザインの考え方が重視され、設計段階から組み込むことが求められています。
- ・廊下やドア幅の確保、段差解消など移動のしやすさ
- ・エレベーターやスロープの設置
- ・車椅子利用者が使いやすい客室や水回りの配置
BIMを活用した効率的な設計シミュレーション
近年はBIM(Building Information Modeling)の活用によって、設計精度と効率性を高める事例が増えています。ixreaでもBIMを導入し、設計段階でのリスクを軽減しています。
- ・避難経路やスタッフ動線を3Dでシミュレーション
- ・設備機器の配置やメンテナンス性を事前検証
- ・設計変更や追加工事リスクを削減し、工期短縮と運営コスト最適化を実現
既存建物を宿泊施設に転用する際の注意点

古民家や空きビルを宿泊施設へリノベーションするケースは増えていますが、新築以上に法規制の壁が大きいのが実態です。特に注意すべきは「用途変更」と「既存不適格」、そして「消防・衛生対応」です。
用途変更が必要となる条件(200㎡超/用途区分変更)
200㎡を超える建物を宿泊用途に変える場合、建築基準法に基づく「用途変更」の確認申請が必要です。これを見落とすと、設計や工事が進んでも営業許可が下りない事態につながります。
- ・「住宅」から「旅館・ホテル」など用途区分が変わる場合に必須
- ・200㎡以下でも大規模改修を伴う場合は対象になることがある
- ・行政協議を早めに行い、用途変更が必要かどうかを確認することが重要
- ・構造安全性・避難計画・内装制限など、現行基準に適合しているかの再確認も必要
既存不適格建物の落とし穴
既存建物は建築当時の基準で建てられているため、現行法に適合していない部分が見つかることがあります。こうした「既存不適格」を見落とすと、改修コストが膨らむリスクがあります。
- ・階段の勾配や幅が現行基準を満たさない
- ・天井高さが不足している
- ・内装材が不燃化基準に適合していない
- ・耐震基準を満たしていないケースもある
➡ 設計段階で詳細調査を行い、追加工事の可能性を早期に把握することが大切です。
消防・衛生面での追加工事リスク
既存建物を宿泊用途に転用する際、消防法や衛生基準の不足が指摘されることは少なくありません。
- ・排煙設備や避難経路の不足は消防検査で指摘されやすい
- ・窓のない客室は使用不可となる可能性がある
- ・換気・給排水・トイレ数など衛生基準を満たさないと営業許可が下りない
➡ 設計事務所としては、事前に消防・保健所との協議を設計フローに組み込むことを強く推奨します。
既存建物を転用する場合は、「用途変更」「既存不適格」「消防・衛生対応」の3点を設計段階で徹底的にチェックすることが、運営開始後のトラブルや追加コストを大幅に減らすカギとなります。
ixreaでは、事前調査・行政協議・消防事前相談を一括で対応できる体制を整えており、既存建物の診断から用途変更申請まで幅広くサポートしています。
宿泊施設設計にかかる費用と補助金・資金調達の方法
宿泊施設の設計には、建設費や設計費に加えて、補助金・助成金を活用できるかどうかが資金計画を大きく左右します。ここでは、費用の目安とあわせて押さえておくべきポイントを整理します。
新築とリノベーションの費用目安
宿泊施設の建設費は規模やグレードによって大きく変動します。
- 新築:小規模(20〜30室)で約5〜10億円、中規模(50〜100室)で15〜30億円が目安です。
- リノベーション:規模や改修範囲によって数千万円〜数億円に及びます。
設計費用の相場と設計監理料
設計費用は建築費全体の5〜12%程度が一般的です。小規模案件では8〜12%と割合が高く、大規模案件では5〜8%に抑えられる傾向があります。
また、設計事務所の関与範囲によっても費用は変動します。基本設計だけなのか、施工監理まで含むのかを早めに明確化することで、予算計画が立てやすくなります。
補助金・助成金の活用
宿泊施設設計においては、補助金や助成金の活用も有効です。
- ・省エネ設備や再生可能エネルギーの導入を支援する制度
- ・観光庁や自治体による観光振興補助金
- ・空き家活用や地域活性化を目的とした助成制度
これらの制度は年度ごとに条件や対象が変わるため、設計段階から調査して計画に反映することが、工期短縮やコスト最適化につながります。
宿泊施設設計を成功に導くためのパートナー選びのコツ
宿泊施設の設計は、住宅やオフィスとは異なり、建築基準法や旅館業法など複数の法規制に対応しながら進める必要があります。そのため、設計パートナーの選定はプロジェクトの成否を左右します。ここでは、設計事務所を選ぶ際に重視すべきポイントを解説します。
宿泊施設設計の実績と法規対応力
宿泊施設の案件経験が豊富で、法規に精通しているかどうかは最重要ポイントです。特に用途変更や旅館業法の要件を満たすためには、一般住宅の設計とは異なるノウハウが不可欠です。
行政協議や消防相談をサポートできるか
宿泊施設の設計では、行政や消防との協議が必須となります。事務所によってはこれらを一括で代行でき、計画をスムーズに進められるかどうかが大きな差となります。事前協議の調整力がある設計事務所は、安心感につながります。
長期的なアフターフォローの有無
宿泊施設は運営開始後も、法改正や設備更新への対応が欠かせません。長期的に伴走してくれる設計事務所を選ぶことで、継続的に相談できる体制を確保できます。改修や増築の際も同じ設計者が関与できれば、整合性の取れたプランニングが可能です
宿泊施設設計を成功に導くために

宿泊施設は「泊まる空間」であると同時に、地域の魅力を発信する拠点です。安心・安全・快適性を確保しつつ、建築基準法や旅館業法などの法制度に適合させることが、プロジェクト成功のカギとなります。
ixreaでは、法制度対応から用途変更、消防協議、BIMを活用した効率的な設計までをワンストップで支援しています。特に以下の点を強みとし、発注者が安心してプロジェクトを進められる体制を整えています。
ixreaの強み
- 建築基準法と旅館業法を両軸で設計に反映
- 用途変更・消防法対応をワンストップで支援
- 民泊・ホテル・簡易宿所まで幅広く対応可能
- BIM活用でコストと工期を最適化
宿泊施設の設計を検討されている方は、事業構想の初期段階からでも、既存建物の転用に関するご相談でもお気軽にお問い合わせください。